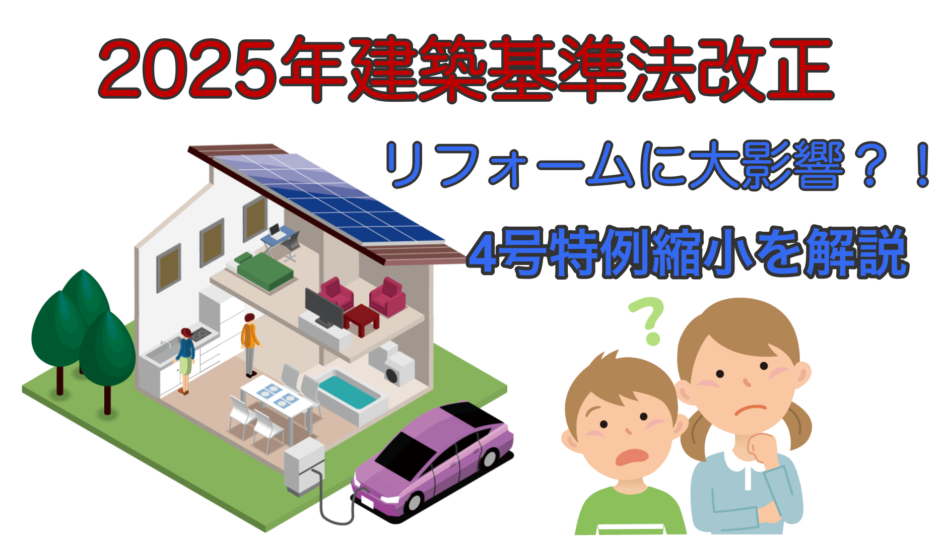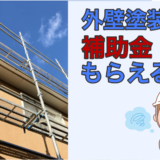【PR】
2025年4月から建築基準法の改正がありました。
「4号特例の縮小」と呼ばれて、国土交通省のホームページやネット等でも多くの情報が流れています。
4号特例の縮小と言われても「何それ?」って感じる方も多いでしょう。
超簡単に解説すると、
お家のリフォームする内容が、建築基準法に違反していないか審査を行い(確認申請と呼ばれてます)、適合の場合には合格証として「確認済証」を受ける手続きが必要になることです。
今までは、この確認申請が必要なかった工事だったが、これからは必要になると言われると不安を感じます。
この記事では、建築に関する専門知識がない方のために、わかりやすく
- 何が変わるの?
- どんなリフォームに影響が出るの?
- どんな問題が発生するの?
などについて解説をします。

えごう はるひこ
約40年の建設業界経験を持ち、設計・施工・営業を含む幅広い分野に従事。建築士、宅建士、FPなどの資格を活かし、専門の知識と経験をもとに役立つ情報をブログで発信しています。
建築基準法の4号特例ってなに?縮小される?
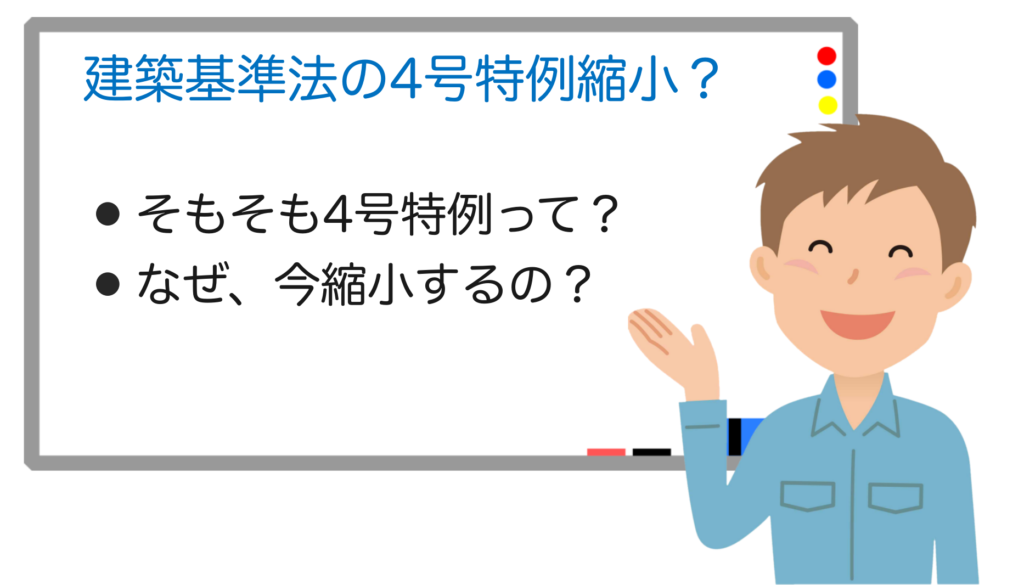
ここでは、4号特例ってどんな内容なのか?
それが縮小されるってどんなことかについて解説します。
そもそも4号特例ってなに?
建築基準法では、建物の設計が終わるとこれから建設する建物が建築基準法に違反していないか?を役所や指定検査機関で審査することを確認申請と呼ばれています。
この審査に合格後に確認済証を受領できて、初めて工事の着工が可能になるんです。
しかし、すべての建物を建築するときに確認申請が必要になるのではなく、確認申請が必要な建物と不要な建物の線引きを行っています。
この確認申請は不要としていた建物の種類を4号建築物と呼び特例として確認申請を不要とした。
建築士や大工さんの知識と経験と責任と信頼で工事ができる仕組みを作り、申請等の手間をかけずに住宅建築をスムーズに行えた経済優先の制度でした。
4号特例が縮小ってどういうこと?
特例で確認申請が不要だった小規模住宅の範囲を縮小して、ほとんどの小規模住宅もこれからは、確認申請が必要になるってことです。
ここで以前の4号特例で確認申請が不要だった建物がこれからはどう変わるのかを表にしてみました。
| 種類 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 木造平屋建て (200㎡以下) | 不要(旧4号) | 不要(新3号) |
| 木造平屋建て (200㎡超) | 不要(旧4号) | 必要(新2号) |
| 木造2階建て | 不要(旧4号) | 必要(新2号) |
| 木造3階建て 以上など | 必要(2号) | 必要(2号) |
なぜ、その特例を縮小されるのか?
確認申請を行う手間や費用がかかってでも、なぜ法改正で4号特例が縮小されるのかを解説します。
これまでは、新築住宅の着工戸数を増やすことで、経済の景気アップを図ることで上向き成長をしてきましたが、
今後は、
- 空き家が増加する中、新築住宅を促進するより、省エネや安全性重視の価値ある住宅を増やす
- カーボンニュートラル目指し、省エネ性能向上の義務化をして省エネ対策が不十分な住宅を減らす
- 耐震性能向上し構造的安全性を確保する
4号特例は1980年代の約25年前に経済成長を支えるための制度でした。
現在は、安全で快適な省エネ住宅を長期間使うことに時代がシフトしている。
今回の改正により何が変わるの?
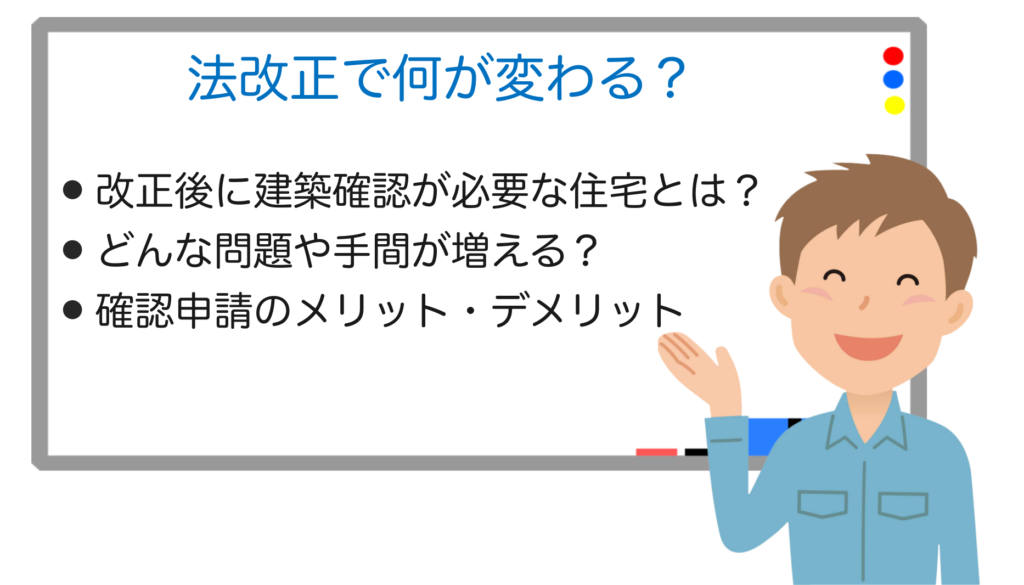
建築基準法の4号特例の縮小について解説しましたので、ここからは、何がどのように変わるのかを解説いたします。
法改正後の確認申請が必要な住宅とは?
木造2階建の新築は新2号建築物と分類がされ、確認申請が必要になる
木造平屋建て200m2以下の新築は、新3号と分類され、確認申請は不要
ほとんどの住宅は確認申請が必要になってことです。
| 種類 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 木造平屋建て (200㎡以下) | 不要(旧4号) | 不要(新3号) |
| 木造平屋建て (200㎡超) | 不要(旧4号) | 必要(新2号) |
| 木造2階建て | 不要(旧4号) | 必要(新2号) |
| 木造3階建て 以上など | 必要(2号) | 必要(2号) |
確認申請が必要になるとどんな問題や手間が増えるの?
どんな問題や手間が増えるのか?
簡単に説明しますと、
- 設計図等の図面以外に多くの書類を作成
- 必要な書類を揃えて役所等に申請を行う
- 工事中の中間検査や完了検査が実施される
などになります。
なので、請負っている工務店や住宅会社の仕事が倍増することになります。
確認申請のメリット・デメリット
確認申請をすることで発注する側(施主)にとってメリットとデメリットをまとめてみました。
- 違法建築になるリスクが低い
- 境界線問題・建蔽率・高さ制限など建築後のトラブルを避けらる
- 確認済証や検査済証があると信頼が高まり売却時にも有利
- 第三者のチェックがあるので、設計ミスや安全性のミスなどを防げる
- 適正にリフォームされた証拠となり、資産価値としてプラスになる
- 書類準備や役所とのやりとりで手間と時間がかかり、工事が遅れる可能性も
- 書類の作成料や確認申請費用など追加コストが発生
- 確認済証の受取後の工事開始となり予定通り進まない可能性もあり
- 法令の制限によりイメージ通りにデザインに制限が出る場合あり、設計の自由度は下がる
- 審査中に設計の変更を求められる可能性もあり
リフォームではどんな影響があるの?
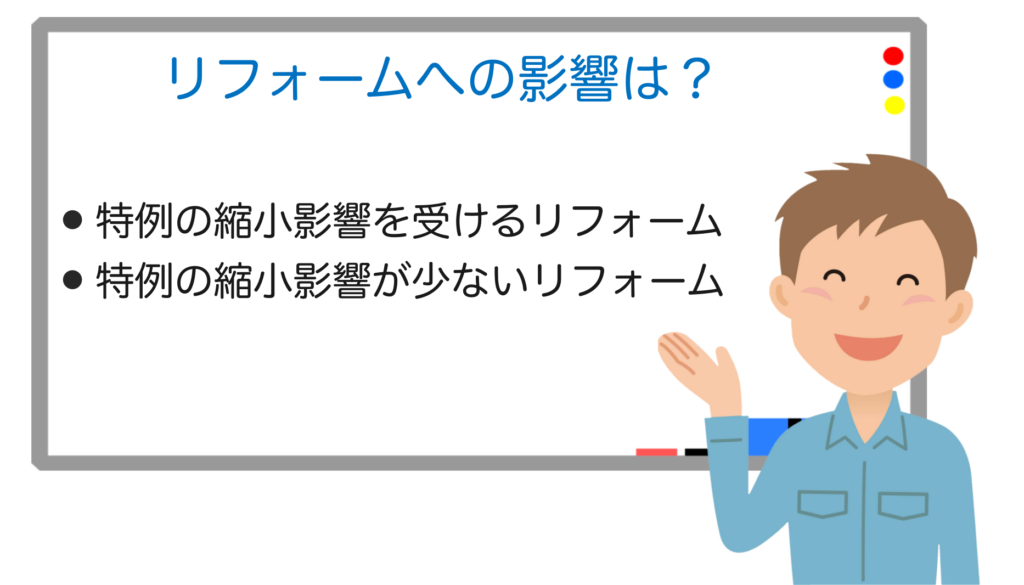
4号特例の縮小は基本的に新築工事の場合について解説してきました。
リフォームを行うにあたり、何か影響はあるの?と感じます。
ここからは、リフォームを行うにあたり、どんな影響を受けるのかを解説します。
4号特例の縮小影響を受けるリフォーム
基本的に4号特例縮小の影響を受けるリフォームは、建築面積の半分を超える大規模リフォーム。
どんな場合が大規模リフォームに該当するのか例をあげてみました。
建物の内装や下地、設備等をすべて撤去し、柱や梁だけの構造体の状態から仕上げていく工事です。リノベーションと呼ばれることも。
床・壁・屋根などの大部分を修繕することになり、大規模リフォームになります。
前記のスケルトンリフォームまでではないが、部屋の壁位置を見直し、壁や柱の位置を変更するリフォームです。
例えば、リビングとダイニングをつなげて広い空間にするために、耐力壁を作ったり、柱を追加する等の工事が該当。
老朽化した屋根下地を取り替えや修繕を行ったり、構造変更を行うような修繕。
例えば、屋根の下地材である、野地板や垂木など全面の半分を超える交換を行う場合やカバー工法で全面的に新たに覆い被せる等荷重条件が変わる場合
屋根全体の葺き替え修繕を行う場合も対象になる可能性あり
老朽化した外壁を全面的に修繕する工事
例えば、経年劣化した外壁材を撤去し、外壁を受ける下地材の修繕や耐震性の向上のため、壁下地を補強と同時に断熱材を入れ替えする等の工事。
建物内部の階段を新しく付け直したり、または、間取りの変更に伴い階段の位置を変更、移設した場合等
地震に備えて耐震性を高めるための工事。
壁を壊さずに筋交いや合板で耐力壁を増やしたり、床に梁や火打ち材を追加して補強をする場合など
既存の住宅に横方向に部屋を増やしたり、平屋の上に部屋を増やすなど、建築面積や延べ面積を増やす増築工事
老朽化した家の一部を壊して、新たに部屋を作り直すリフォーム
主な大規模リフォームの例について解説をしましたが、判断が難しい場合が多くあるでしょう。
自治体の担当窓口に事前に相談をすることがおすすめです。
4号特例の縮小影響が少ないリフォーム
建物の構造に影響しない部分や壁・柱・梁・階段・屋根の改修範囲にが過半に満たない小規模なリフォームであれば、確認申請は不要です。
ここでは、4号特例の縮小でも確認申請の不要な影響の少ないリフォームの例を紹介します。
床の仕上げ材を変える内装工事なので建物の構造部には影響を与えません。
壁のクロスを新しく張り替えたり、塗料で塗り直す等のリフォームは不要
システムキッチンを新しく交換したり、レイアウトを大きく変更しない範囲では
構造に大きく影響しないので申請は不要
古い在来工法の浴室をユニットバスに入れ替えや既存のユニットバスを新しいユニットバスに交換も申請は不要
設備更新に模様替えになります。
室内のレイアウト変更で構造的に荷重を受けない間仕切りを撤去したり、新設することは申請不要。
ただし、耐力壁など荷重を受ける壁を取り除くなどの場合は、構造的に安全性の問題があるので申請が必要な場合もある。
老朽化した屋根の一部を補修したり、瓦の葺き替え工事等は申請不要
屋根全体の場合であっても、既存の下地構造の修繕が過半にならない場合は、申請不要。
屋根全体を一新するような大規模な葺き替えは申請の必要がある。
建物全体の外壁の塗装や傷んだ外壁材の部分的な張り替えを行うリフォームは申請不要
ただし、外壁の使用を大幅に変更する場合や建物全体の外壁補修を行う場合は申請が必要
古い単板ガラスの窓をペアガラスサッシに交換
玄関ドアを断熱性の高いドアに交換
ただし、窓の位置変更や大きさを変える等は、構造的に影響があり申請が必要になる場合も。
既存住宅の省エネ性能向上のため、壁の内部に断熱材を充填
天井裏にグラスウール設置等は不要
木造平屋建ての大規模リフォームの場合も申請は不要
影響を受けるリフォームの場合と同じく、事前に自治体の担当窓口の相談することがおすすめ
注意すべき4つの特殊ケース
再建築不可物件のリフォームはどうなる?
道路接道義務などの問題で再建築不可能とされている住宅は、前記した確認申請が必要になる大規模リフォームは不可能な可能性が大きい。
確認申請が降りないために、工事開始できないのです。
建築基準法違反のままの物件
すでに建築基準法違反となっている住宅は、前記した確認申請が必要になる大規模リフォームを行う場合には、違反をしている内容について是正を求められる。
例えば
- 無申請による増築
- 容積率や建蔽率オーバー
- 用途地域の違反
- カーポートや物置が建築面積に含まれる
など
旧耐震基準で建てられた住宅の大規模修繕
1981年以前に建てられた木造2階建の古民家再生のような大規模修繕を行う場合は基本的に確認申請が必要になるため多くの検討事項が発生することもあり、
- 耐震に対する構造計算と耐震補強
- 現行耐震基準に適合するための構造計算が必要
- そのために建物全体の耐震補強工事が必要となる。
- 省エネ基準への適合
古民家などは断熱性が低いため、壁や屋根への断熱材の設置及び窓等を省エネサッシに交換等が必要になり、省エネルギー性能の確保が必要
古民家再生リフォームに十分に経験と知識のあるリフォーム会社に相談や発注する必要があります。
確認申請をするための既存建物の図面がない
木造2階建住宅を大規模リフォームを行うには、確認申請が必要になります。
しかし、古民家や古い住宅なのでは、建物の図面が無い場合が多くあります。
その場合は、仕上げ材を撤去して現地調査や計測を行って設計図の復元から行う必要がある可能性もあり。
また、過去にリフォームを行ったが、そのリフォームの内容が図面に反映されていなくて、設計図の書き直しが必要な場合もあり。
建築基準法に違反している場合もあるので特に注意が必要です。
発注者(施主)ができる対策とは
4号特例の縮小について概要は理解できたと思います。
メリットもデメリットもありました。
では、現状で発注者がリフォームを成功させるためにできる対策について解説します。
リフォーム会社選びがもっと重要になる
法改正があった場合は、多くの場合に最初は混乱が生じるものです。
今回の4号特例の縮小にあたっては、リフォーム会社選びの際には下記の件について十分に確認をしてください。
- リフォーム会社に確認申請に詳しい建築士が在籍しているか?
- 法改正後の確認申請に対応経験があるか?
- 設計及び施工監理には建築士が必要
「影響はありません!」と安易に言い切る会社は注意が必要
相見積もりで比較・相談を
2〜3社に必ず相見積もりを依頼して、対応力・説明力を比較する
「確認申請が必要ですか?」と質問してみることも大切。
申請が必要になる可能性があるなら、早めの行動を
改正後は一時的に確認申請が混み合い、着工が遅れることもあるでしょう。
リフォームを完了させたい日程が決まっているなら、目標日程から逆算して早めに動き始めるのが良さそうです。
工事を急がないなら、半年~1年様子を見るのも選択肢
まとめ
今回は建築基準法の改正で4号特例の縮小について解説しました。
ポイントは
- すべての人に大きな影響を及ぼず改正ではない。
- 大規模なリフォームや構造体の変更等があるリフォームを行うときには影響あり
- 現状で再建築不可物件や違法建築の場合は確認申請を行う際に支障が出る
- 法改正後の混乱を避け、様子を見ながらリフォーム時期をずらす
うちのリフォームには関係ないと思われるリフォームも法の解釈の仕方によっては、確認申請が必要になる可能性もあります。
将来のことも考え、安心してリフォームをするには、建築基準法の法改正にも詳しい優良リフォーム会社を選ぶことです。
まずは、複数のリフォーム会社に相談・見積もりを依頼して、慎重にリフォーム会社選びを進めること。
リフォーム一括見積もりサイトおすすめ紹介

リフォームの希望や悩みを解決!
おすすめ度
| サイトの信頼性 | |
| サイトの利便性 | |
| 登録会社の質 | |
| 保険・保証 | |
| 電話相談窓口 | |
| 総合評価 |

無料でリフォームプランも貰える
おすすめ度
| サイトの信頼性 | |
| サイトの利便性 | |
| 登録会社の質 | |
| 保険・保証 | |
| 電話相談窓口 | |
| 総合評価 |

優良リフォーム会社の登録が多数あり!
おすすめ度
| サイト信頼性 | |
| サイト利便性 | |
| 登録会社の質 | |
| 保険・保証 | |
| 電話相談窓口 | |
| 総合評価 |
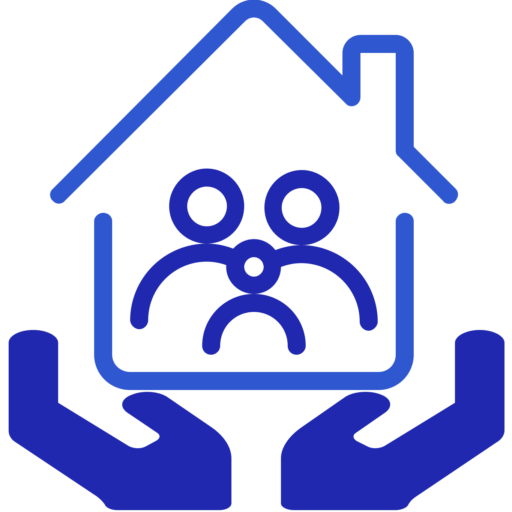 リフォーム・ナビゲーション
リフォーム・ナビゲーション